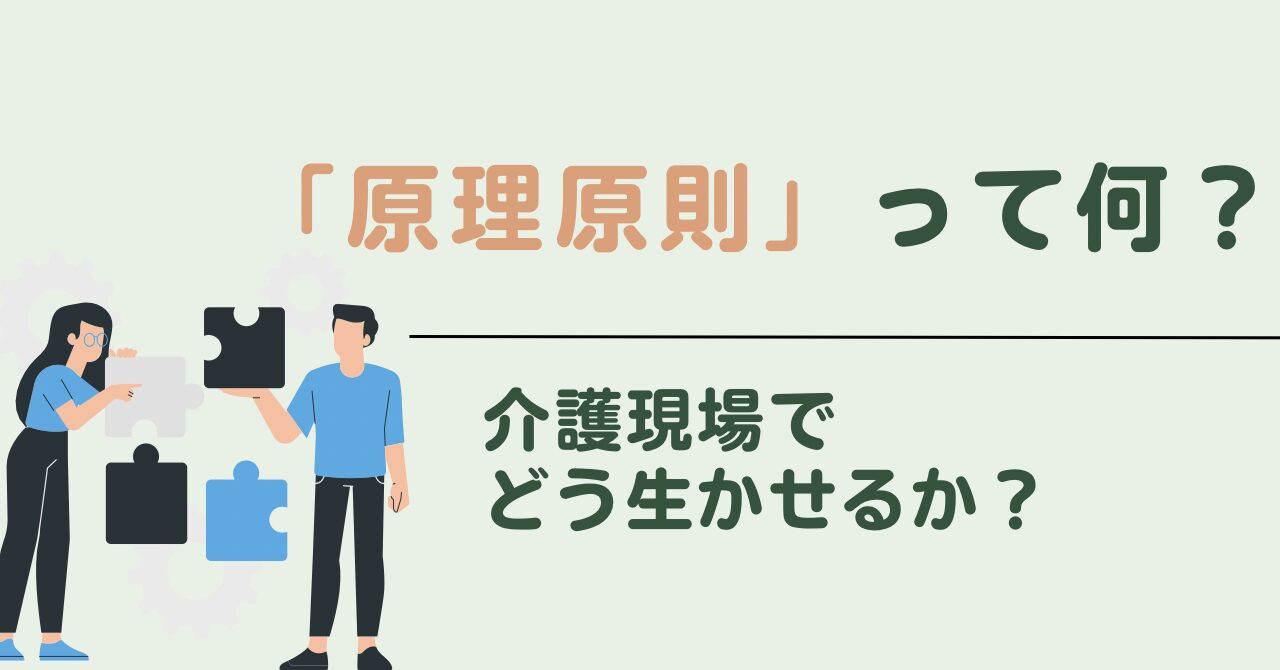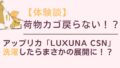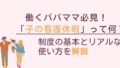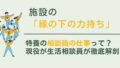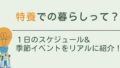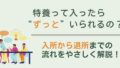こんにちは!特養相談員ママのこむぎです!
他施設の現場で働く夫に、お仕事について相談していたときのこと。

「それって“原理原則”に沿って考えるといいんだよね」
なんだいなんだい!?
原理原則って、どこの社長から仕入れてきたんだい!?
説明聞いてもハテナマーク??の連発。
何度も聞き返していくうちに、
「あれ…?これ、うちの介護現場にも通じるかも…?」
と思えてきたんです。
今回はその“原理原則”について、
私なりにかみ砕いて考えたことと、現場でどう活かせるか?についてお話ししてみます!
原理原則ってなに?ざっくり解説!

原理原則とは、
「物事の本質的な仕組み・ルール」のこと。
私はポカン。
そんな時、夫が出した例えは
「お金」でした。
「お金持ちが貧困層にお金を払うのって、単なる親切じゃなく、仕組みに基づいているからでしょ?」
「100万円持ってて、何の理由もない人に“ちょうだい”って言われたら渡す?」
んー!なるほど!なんとなく分かった!
介護現場にどう使える?

介護の現場では、
「人手が足りない」
「忙しすぎてまわらない」
「残業ばっかり」
そんな声、日常茶飯事ですよね?
私の職場もまさにそう!
シフト表を見ても明らかに人が少なくて、退職者も続いてるのに、なかなか補充されない…。
応援をお願いしても「人が足りないんで無理です」と断られる。
「いやいや、そっちのフロアには人いるじゃん!」って思っても、
実際には“最低限の業務をカバーできないスタッフ”が多かったり、
身体的に“制限”があったりして、実質的には足りてない、、。
どこもカツカツで、「うちも無理なんで」の押し問答。
…このままじゃずっと平行線
ここで、原理原則の視点で見てみました。
結果、
「なぜ自分たちのフロアに応援が必要なのか」を、
“感情”ではなく“構造”で説明する必要があるんだと分かりました。
- フロアの人数とケア量のバランス
- 退職による業務過多の現状
- 他フロアとの役割分担の不均衡
こういった“事実”をもとに話すことで、応援依頼も“説得”ではなく“納得”に変わる。
ただ「つらい」と言うのではなく、
「なぜ必要なのか」を共有することが大事なんですね!
私なりの“原理原則”の活かし方
とはいえ、「上に報告しました」で終わると、
「言っただけ」になっちゃうんですよね、、。
その中で、私は空気を変える、考え方を変えるきっかけ作りに尽力してみました。
◆ 「噂を流す」

「最近さ〜、○○が大変だってよく聞くけど実際どうなんだろう?どうしたら良くなるんだろうね。こうして見るのはどうなんだろう?」って、
話題にして共通の視点をじわじわ広めるんです。
ただの愚痴や不満が“考えるきっかけ”に変わるチャンスになっていきます。
◆ 言語化できない“モヤモヤ”を代弁する

「連絡が下手」→「仕組みがないから上手くいかないのかも」
「報連相がバラバラ」→「共通の手順が必要かも」
感情のせいにするんじゃなく、構造のせいにすることで、
愚痴や不満で終わせず、話しやすさ・改善しやすさがアップしていきます。
まとめ:現場を動かす“共通認識”をつくろう

いざ実践してみると、自分が楽になりました!
愚痴や不満を無限に聞くのはしんどいですが、
有効活用のきっかけになるかも!と思えることでかなり心が楽になりました。
原理原則って、最初は「なんか小難しい…」って思ったけど、
介護現場でも、意外と効く“考え方のくすり”かもしれません。
ただ「つらい」「なんとかして」って言うんじゃなくて、
“なぜ今そうなってるのか?”
“どうしたらみんなが納得して動けるのか?”
この視点を持つだけで、言葉の届き方も、対話の質も変わる気がします。
もし今、「なんでこの状況、変わらないんだろう?」って思っていることがあるなら、
それは「原理原則で考え直すタイミング」かもしれません。
最後まで読んでくださりありがとうございました!
人気記事も覗いていってくださいね!↓