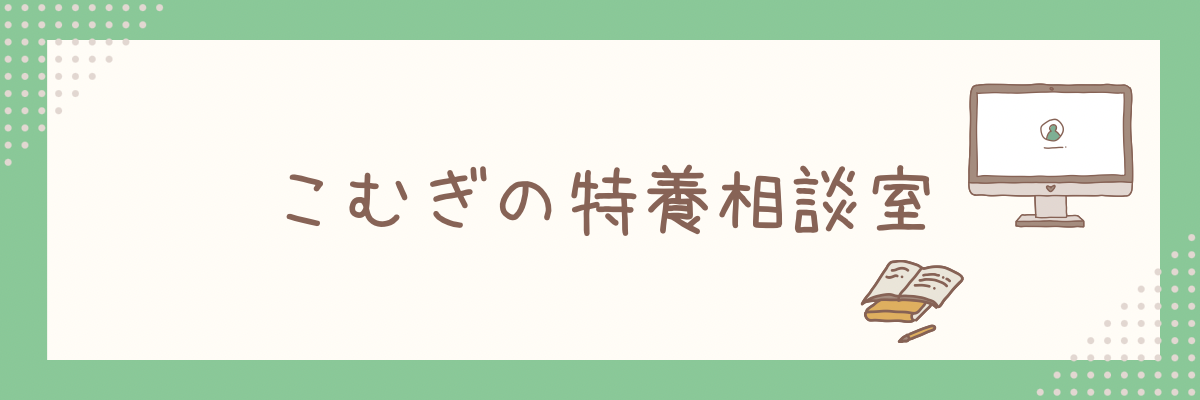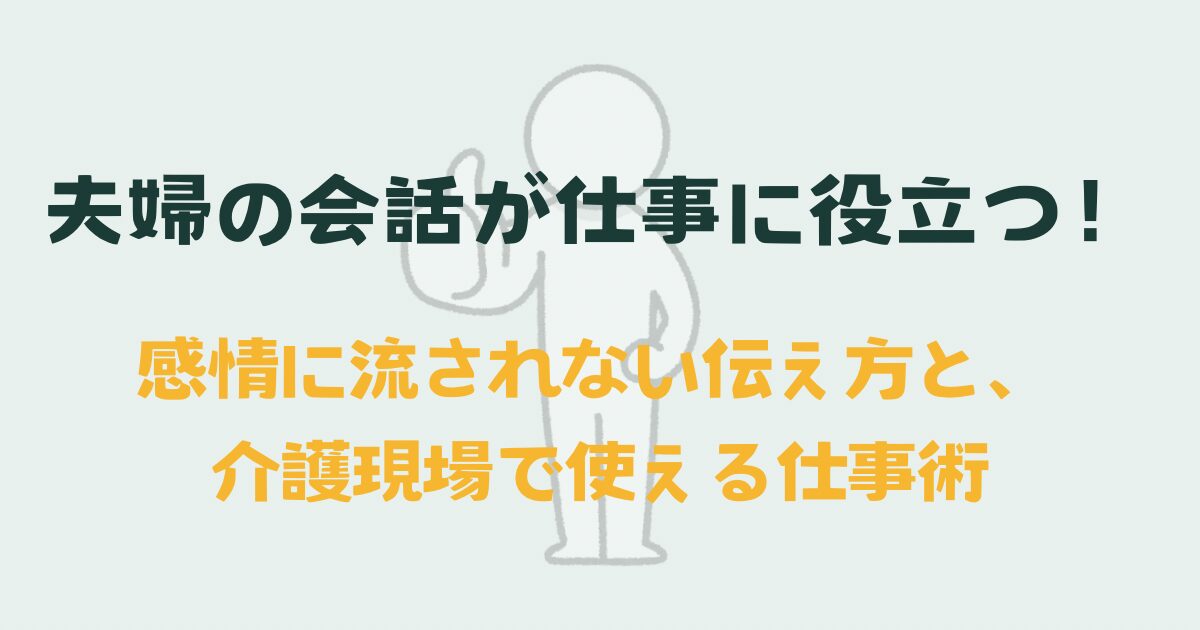- 夫婦の何気ない会話から学んだ、仕事で活かせる考え方
- 介護施設でのコミュニケーションに役立つ3つのコツ
- 相談員・介護職として意識したい「伝え方の工夫」

こんにちは!特養相談員ママのこむぎです

日常のちょっとした夫婦の会話が、意外と仕事に役立つことってありませんか?
私の夫は、出会った5年以上前から、
YouTubeでビジネスや仕事術を学び続けていて、介護職の中でも「考え方がちょっと違う珍しい人」なんです。
最初は、話を聞いても「何語?😅」と感じることも多かったのです。
だんだんと
「これ、相談員の仕事でも役立つかも!」と思えることが増えてきました。
今日は、夫との会話から学んだ、介護施設で働く人にとっても役立つ伝え方のコツをシェアします。
夫が意識している仕事のキーワード
最近の夫が意識している言葉は、こちらの5つ。
- 再現性(誰でも同じようにできるか)
- 浸透率(ちゃんと伝わっているか)
- 解像度(どこまで具体的にイメージできるか)
- 明確化(あいまいなことをハッキリさせる)
- 数値化(感覚じゃなく数字で表す)
横文字ばかりだった時期もありましたが、今はできるだけ日本語にして伝えるようにしているそうです。(分かりやすい!!)

相手が理解しやすい言葉を選ぶと、余計なモヤモヤが生まれにくい。
パターン化しておくと、やり取りもスムーズになる。
介護の現場でも、ご利用者様・職員・ご家族様・業者の方など、
相手によって意識して話し方を変えるのは目から鱗でした。
感情で話さない・言葉の意味をそろえる

夫から学んだ大事なポイントは2つ。
- 感情的に話さない
- 言葉の定義をそろえる
同じ言葉でも、人によってイメージが違うと誤解が生まれます。
「この場ではこの意味で使おうね」と定義づけをしておくと、話がブレにくくなるんです。
代替案の有無でスタンスを変える

さらに夫が意識しているのは、
自分に代替案(別の提案)があるかどうかで、話し方を変えること。

代案があるときは自信をもって提案。
ないときはまず受け止めて、次に備える。
相談員の仕事でも、代案があるときはスムーズですが、ないときは一度受け止める方が円滑に進みますよね。
まとめ

- 再現性・浸透率・解像度・明確化・数値化を意識すると仕事が整理しやすい
- 感情に流されず、言葉の意味をそろえると誤解が減る
- 代案があるときは強気、ないときは受け止めると円滑
夫婦の何気ない会話からでも、現場で使える学びはたくさんあります。
私の場合は、 「感情に流されない・意味をそろえる・代案で話し方を変える」
まずはこの3つ!明日から意識してみます!
最後まで読んでくださりありがとうございました!