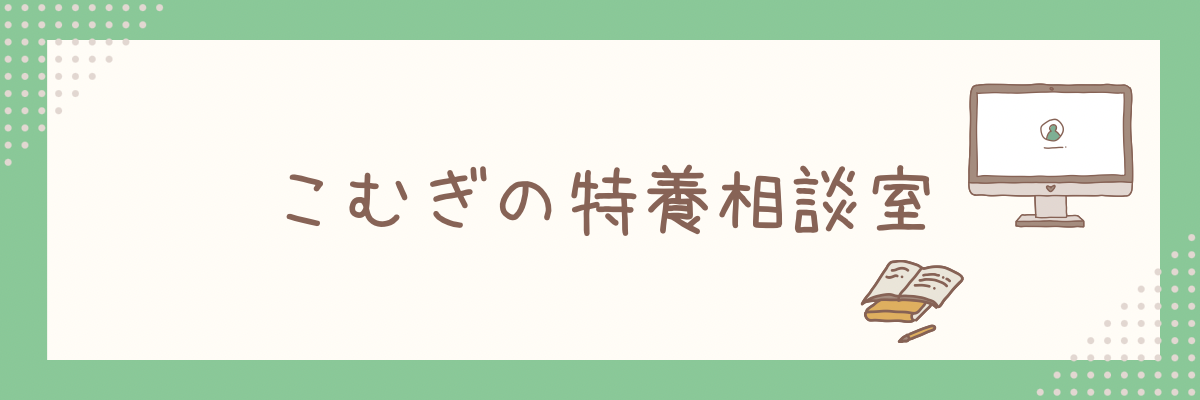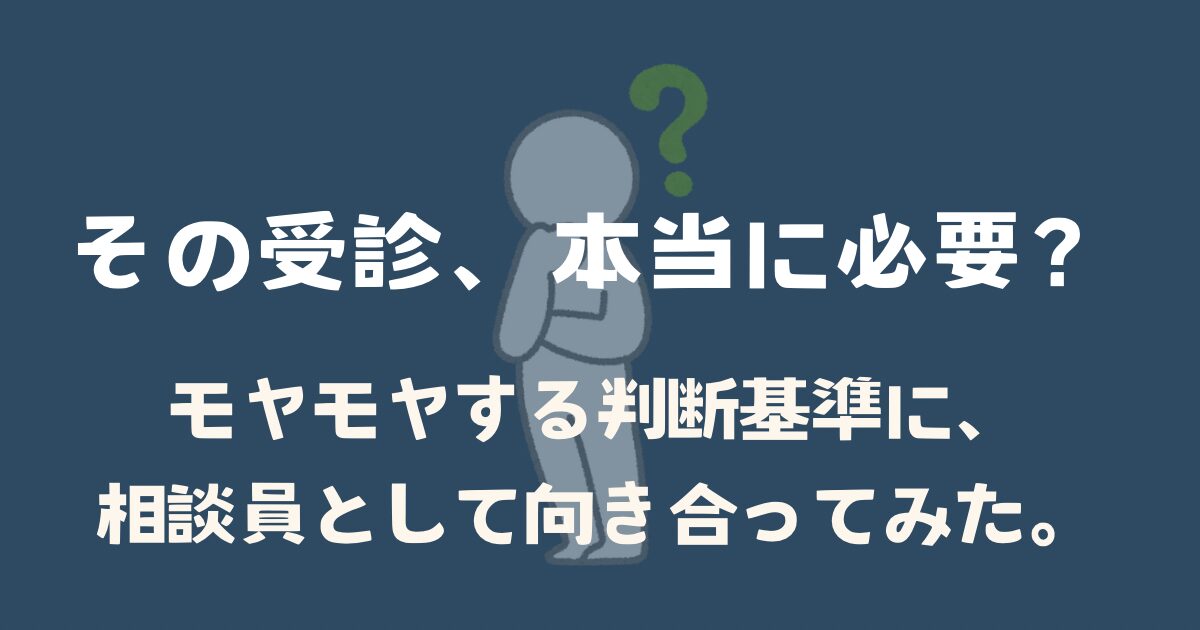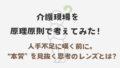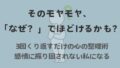こんにちは!特養相談員ママのこむぎです!
特養などの施設で働いていると、ふと感じるモヤモヤってありませんか?
今回はその中でも、「病院受診の判断」についてのお話です。
「あれ、また私が付き添い?」「昨日は様子見だったのに…今日は?」
そんな場面に心あたりがある方へ。
このブログでは、相談員として現場で感じたリアルな葛藤と、少しずつ見えてきた工夫や視点をまとめてみました。
同じように感じている誰かの、ヒントや安心につながったらうれしいです🍀
「受診、行けますか?」…え、また私?
ある日、看護師さんからのひと言。
「○○さん、熱が少しあるので受診お願いできますか?」
…え?37.2℃?
昨日も似たようなケースあったけど、あのときは「様子見で」と言ってたよね…?
そんな風に、受診の判断基準に違和感やモヤモヤを感じたことはありませんか?
私は正直たくさんあります!!
でも、「受診に行きたくない!」ってことじゃないんです。
イヤなのは“納得できないこと”
私は受診の判断そのものに反発したいわけではなくて、
- 「この受診、誰のため?」
- 「なんで今回は行って、あのときは行かなかったの?」
っていう基準のあいまいさに戸惑ってしまうんです。
そもそも、明確な基準はない
特養の受診対応って、各施設に判断が委ねられているんですねよね。
主治医と連携しながら施設ごとにルールを決めて対応する…というのが基本スタンス。
でも、そのルールすら「なんとなく」の共有で進んでること、ありませんか?
看護師と介護職、視点のズレ
受診の判断をするのは、多くの場合看護師さん。
でも、看護師さんはどうしても医療面の数値やリスクを重視しがちで、
一方で、私たち相談員や介護職は、日常生活の“その人らしさ”に目が向きます。
たとえば…
- 「37.2℃の微熱でも、○○さんは毎回体調崩すから念のため」
- 「この人は普段から波があるし、今日はごはんも食べてるから様子見でもいいかも」
こんなふうに、同じ数値でも見方が違うんですよね。
「誰が付き添うか」によっても変わる?
また、地味に大きいのがこれ。
受診の付き添い、誰が行くの?問題。
- ご家族:「何かあるたびに呼ばないで!」「また病院?」
- 職員:「え、また私?」「それって今すぐ行く必要あるの…?」
受診って、物理的にも心理的にも“重さ”のある業務。
その負担感が、判断にも影響してる気がします。
私の思う「特養=自宅の延長」の考え方
私は社会福祉士、介護支援専門として、
「特養は自宅の延長」という言葉を大切にしています。
自宅だったら…
・熱が出たからすぐに病院行きますか?
・一食ごはん食べなかったからって、すぐ受診しますか?
そう考えると、
“施設だから”病院に行く、という感覚には少し疑問もあります。
もちろん、医療的なリスクを軽く見ていいとは思いません。
でも、「生活の延長としての安心」も大切にしたい。
視点が違うから、ぶつかって当然
看護師さんは医療の視点、
介護職さんは生活の視点、
そして相談員は家族との関係も見ながら調整する立場。
見ているものが違うから、受診の判断に違いが出るのは当然なんです。
だからこそ大事なのは、
- 「ここだけは!」という共通の視点をつくること
- それを言語化してルールに落とし込むこと
- そして、現場の声に合わせて見直していくこと
おわりに:モヤモヤを、見える化していこう
受診判断に正解はありません。
でも、「なんでモヤモヤするのか」「自分はどう思ってるのか」を見える化していくことで、チームでの連携はぐっとスムーズになります。
もし、今あなたが
「また受診?」「今回は行かないの?」
と感じているなら、それはおかしなことじゃありません。
むしろ、気づけているからこその葛藤なんだと思います。